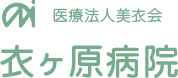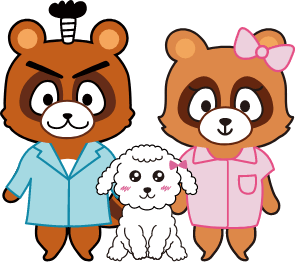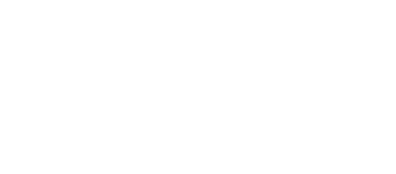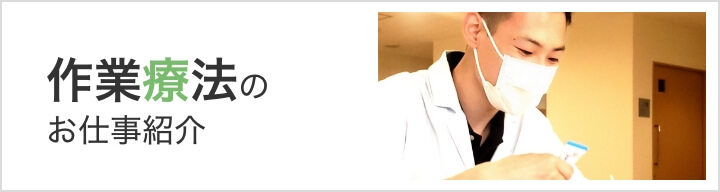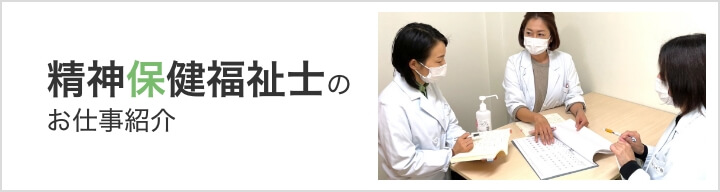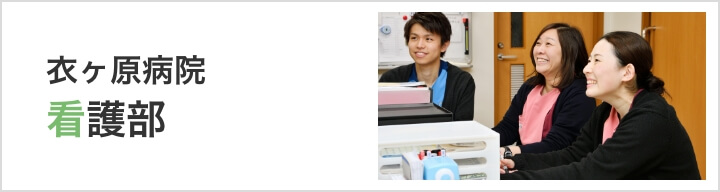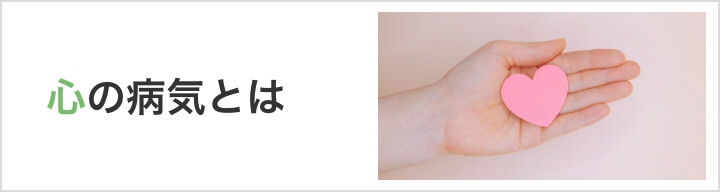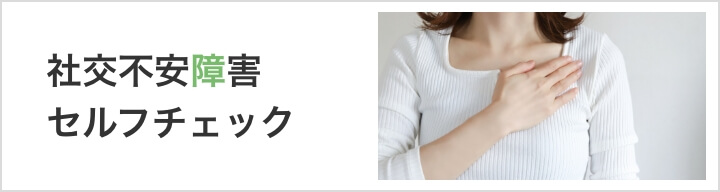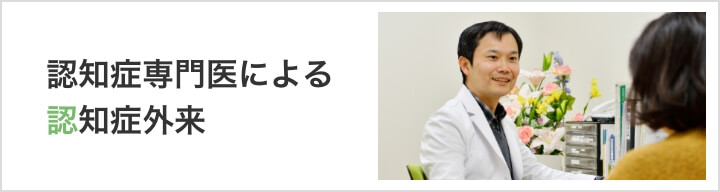2024.09.4 うつ病
ストレスを受け流せるようにしよう‼~うつ病などの時の思考パターン(考え方のクセ)~
こころの病(うつ病など)について
こころの病(うつ病など)は、薬物療法で症状がよくなっても、再発しやすい病気です。
その要因の一つとしてストレス(日常生活上などの)があります。
たとえ一時改善しても、社会に出てストレスにさらされてしまうと再び悪化してしまうこともあるため、ストレスの受け流し方を考える必要があります。

ストレスと認知
そもそも私たちはストレスをどのように感じているのでしょうか。
私たちは、ものごとを受けとめ「認知」しています。
その物事をどのように受けとめて感じるかにより、「よいこと」「よくないこと」かにわけています。
こころの病(うつ病など)がある人は、その認知にクセがあり、ものごとをマイナスに受けとめたり思いこんだりすることがあります。
つまり、こうした物事のとらえ方を修正していけば、病気の悪化を防ぐことができるでしょう。
思考パターン(考え方のクセ)
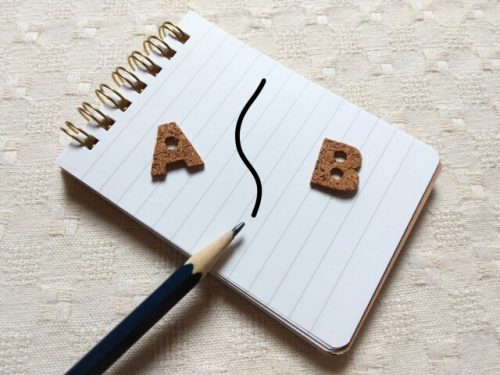
うつ病などでのよく起こりがちな考え方のクセには次のようなものがあります。
・過剰な一般化・・・ネガティブなできごとを、一般的なことと思い込むこと。仕事上のミスをすると、人生が終わったような思いにとらわれたりします。
・ネガティブ思考・・・良いことも悪い方へと解釈します
・結論の飛躍・・・物事の最悪の結論を予測してしまう。友人を誘ったら断られた、注意されたことなどを「自分のことが嫌い、嫌われている」と思い込む
・全か無か思考・・・100点がとれなければ0点と同じだと思う
このようなパターンに陥ってないか?
どんな時にどの思考パターンになっているか?
などに気づくことがまずはとても大切になります。
自分の思考のクセを理解していく
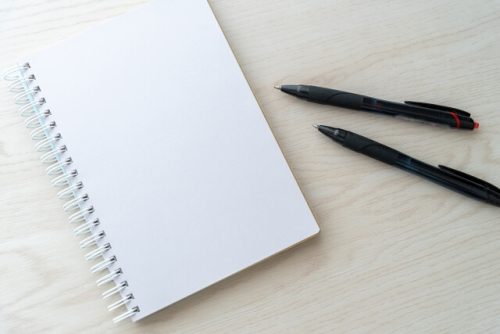
自分のクセに気づくことができたら、どんな時にどの思考パターンに陥りやすいか、何回しているかなどノートなどに記載していきます。
これができたら、今度は「こういう風に考えているけど、こういう考え方もあるね」という可能性を書いていきます。
その可能性のなかから、自分で受け入れやすそうなものを選び「~するのもよい」という考え方をするようにしていきます。
初めは難しいと思われますが、繰り返していくうちに徐々に自分の思考のクセを理解していくことができるようになってくるのです。
リハビリ、治療のご相談は専門家へ

当院では、気分障害などによる認知リハビリとして、認知リハ室「ここわ」を開設しております。
そこでは、遂行機能や作動記憶などの脳の基礎的な力である神経認知機能の改善ための「V-CATJ」、考え方のクセの修正のための「集団認知行動療法」、メタ認知/社会的認知リハビリとして「D-MCT、MCT」を取り入れています。
各種プログラムは、外来患者さんやリワークデイケア利用者さんなどにむけて行っています。
ご興味のある方は、各種プログラムをご利用してみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
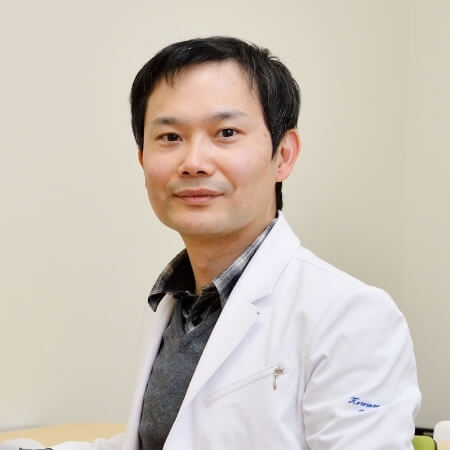
副理事長 加藤 豊文
精神科医
精神保健指定医
認定産業医、精神科専門医・指導医(日本専門医機構)
認知症診療医(日本精神神経学会)
認知症臨床専門医(日本精神科医学会)
認知症サポート医
老年精神医学会認定医
臨床研修指導医
児童思春期精神医学対策講習会スタンダードコース終了(日本精神科病院協会)
児童思春期精神医学対策講習会アドバンスコースⅠ終了(日本精神科病院協会)
産業保健アドバイザー
名古屋平成看護医療専門学校 看護学科 非常勤講師
| 専門分野等 | 精神医学一般、うつ病リワーク、認知症 |
|---|---|
| 所属学会 | 日本精神神経学会、日本心療内科学会、日本うつ病学会、日本老年精神医学会、日本アロマセラピー学会 MCT-J(メタ認知)ネットワーク会員など |
カテゴリー一覧
- 月別アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
最近の投稿
- 2025.12.17美衣会ライフ 第6回 ころも感謝祭
- 2025.12.10大切なお知らせ 2月25日(水)代診のお知らせ
- 2025.12.10大切なお知らせ 1月28日(水)代診のお知らせ
- 2025.11.25大切なお知らせ 1/17・1/24 加藤豊文医師の診察受付時間変更のお知らせ
- 2025.11.25大切なお知らせ 1月31日(土)代診のお知らせ


その他のご案内
More Information
出版書籍のご案内
Publications
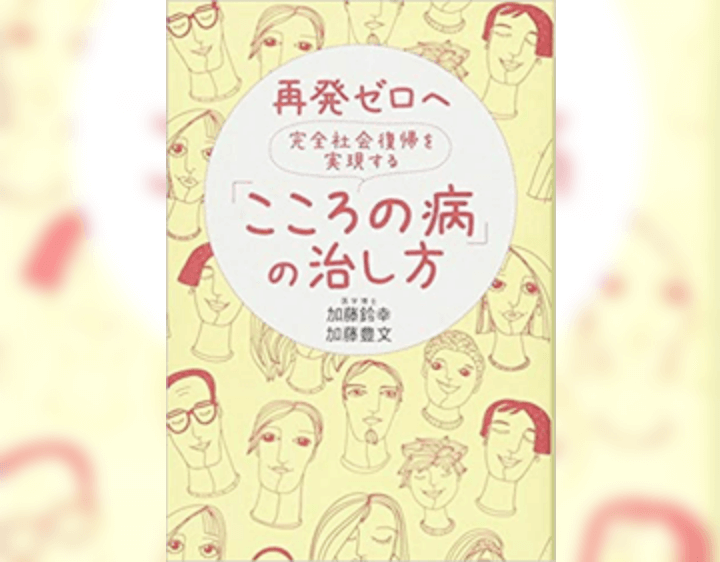
再発ゼロへ 完全社会復帰を実現する
「こころの病」の治し方
当院理事長 加藤鈴幸医師と副理事長 加藤豊文医師の著書が出版されました。
全国の書店またはAmazon等のオンライン書店でご購入いただけます。