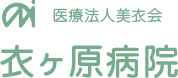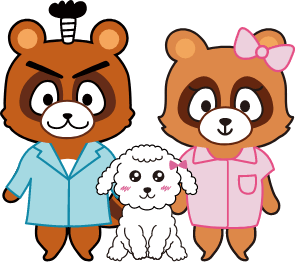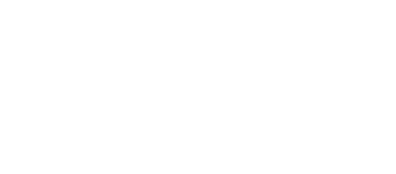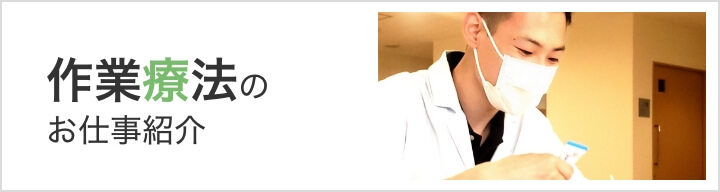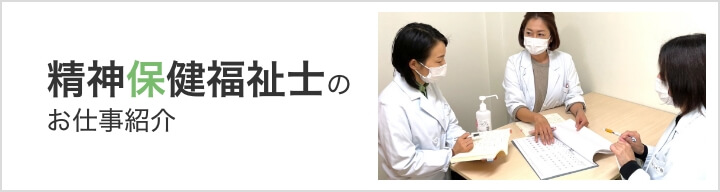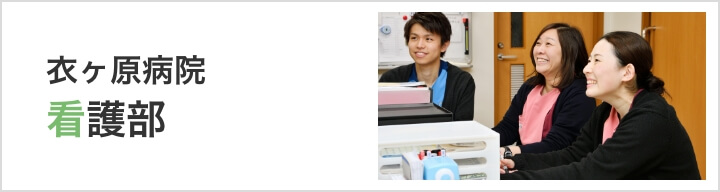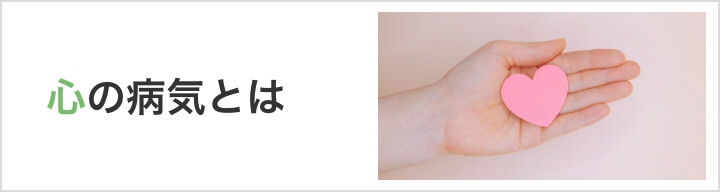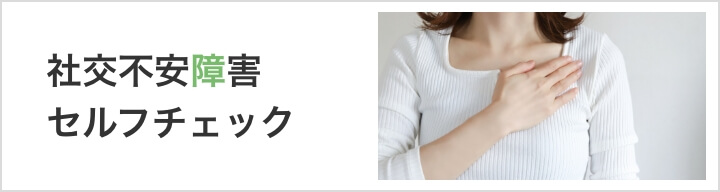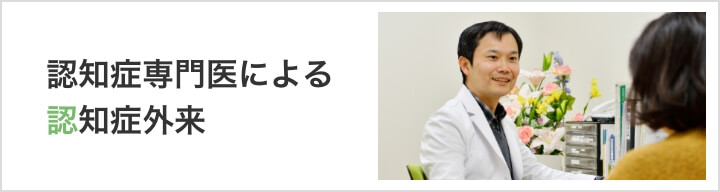2020.11.20 お役立ち情報
緊張しすぎてしまう極度の「あがり症」は心の病?

「あがり症」は心の病なの?
大勢の人の前で話すとき、初対面の人と話すときなど、
日常の生活の中で「緊張」してしまうシーンはたくさんありますよね。
この「緊張してしまう」という状態が極度に強く続いてしまう場合、心の病気の可能性が考えられます。
今回は極度の緊張症状がみられる心の病気である「社交不安症(障害)」についてご紹介いたします。
社交不安症(障害)(SAD)とは

社交不安症(障害)とは、簡単にいうと「あがり症」が極度に悪化してしまい、
・「人前で話すとき、極度に緊張してしまう、ひどい動悸がする」
・「人前で字を書くとき、手が震えてしまう」
といった日常生活に支障が出るほど人前で「強い恐怖」や「不安を感じてしまう」という症状がみられる状態です。
これらの症状がみられる場合、
「内向的」「恥ずかしがり屋」などの人それぞれの気持ちの持ち方や性格的な問題ではなく、
社交不安症(障害)(SAD)の可能性があるといえます。
社交不安症の主な症状

社交不安症の主な症状としては以下のようなものがあります
・人前で発表するのが怖い
・人と接するのがひどく怖い
・周囲からの視線がひどく怖い
・人に注目されると緊張で赤面したりやたらと汗をかく
・人前で食事ができない
・人前で文字を書くとき、手が震えて書けない
・人前で周囲に人がいるとトイレで用を足すことができない
・人前など電話をかけることができない
・お店で店員を呼べない
上記の状況の時に、冷や汗や、動悸、めまい、のどが渇く、頭が真っ白になるなどの
自律神経症状を伴うことしばしばあります。
社交不安症の主な要因

社交不安症の要因としては主に以下の2つのものが考えられます。
(1)生物学的要因
社交不安症(SAD)の人は不安な状況に対し、
健康な人よりも脳の反応が過敏になっていると考えられます。
そのため脳内の神経伝達物質のバランスが乱れてしまい、
「不安」や「恐怖感」を和らげる役目を果たすセロトニンの量が低下していると考えられています。
(2)性格傾向
以下のようなその人がもともと持っている性格的な傾向も主な要因として考えられています。
・真面目で責任感が強い
・心配性
・完璧主義
・人の評価が気になる
・人との交流が苦手
社交不安症の治療

社交不安症(SAD)の治療の柱となる「服薬治療」と「精神療法」をご紹介いたします。
(1)投薬治療
投薬するお薬は、脳内の神経伝達物質(セロトニン)のバランスを整え、不安感や恐怖感を和らげてくれます。
SSRIが第一選択薬とされており、脳内のセロトニンなどの神経伝達物質のバランスを調整していくお薬です。
ほとんどの場合効き目はゆっくりで、効果を実感するのに数週間から数か月かかります。
また、症状が安定しても再発防止のためにある程度継続して飲み続ける必要があります。
(2)精神療法
医師による精神療法や心理士によるカウンセリングなどの心理療法によって
今までの不安に陥りやすい思考の癖に気づき、
自分の思考の癖を理解、問題解決する方法を探っていきます。
あがってしまうのは性格や気持ちの問題?

社交不安症(障害)はその辛さをまわりに理解されにくく、自分の性格の問題だと思いこんでしまい、どこに相談したらよいか迷われることが多いと思います。
しかし、社交不安症(SAD)は、適切に治療をすれば改善する心の病気です。
主に脳の神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスが乱れていることが原因の一つとして考えられるため、
服薬や精神療法を組み合わせながら治療を行っていきます。
一人で抱え込まずにまずは精神科などの専門機関に相談することが大切です。
カテゴリー一覧
- 月別アーカイブ
-
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
最近の投稿
- 2025.04.1大切なお知らせ 加藤豊文医師の診察受付時間変更のお知らせ
- 2025.04.1大切なお知らせ 5月17日(土)代診のお知らせ
- 2025.03.7お役立ち情報 認知症初期症状について〜本人及びご家族の認知症の始まりに気づくポイント〜
- 2025.03.1大切なお知らせ ゴールデンウィークお休みのお知らせ
- 2025.02.20お知らせ 広報誌『こころも』vol.6 発行のお知らせ


その他のご案内
More Information
出版書籍のご案内
Publications
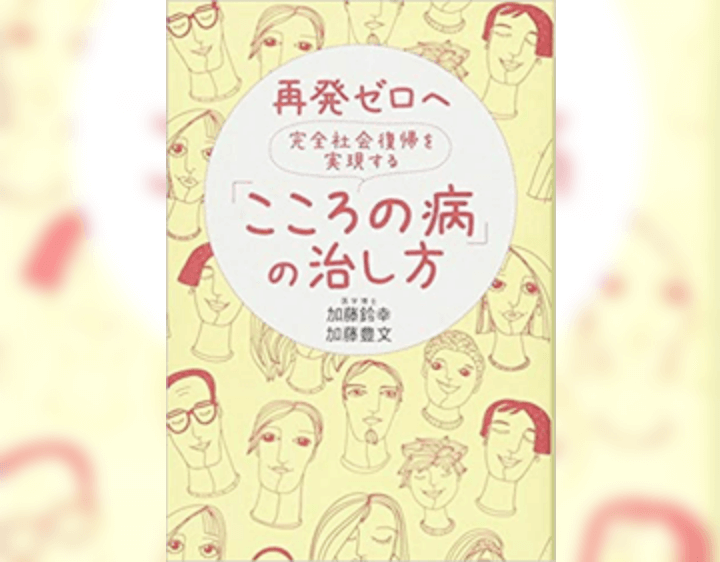
再発ゼロへ 完全社会復帰を実現する
「こころの病」の治し方
当院理事長 加藤鈴幸医師と副理事長 加藤豊文医師の著書が出版されました。
全国の書店またはAmazon等のオンライン書店でご購入いただけます。