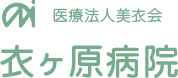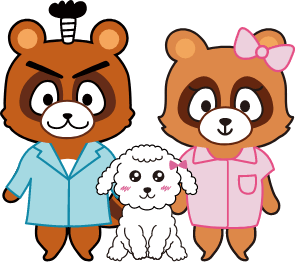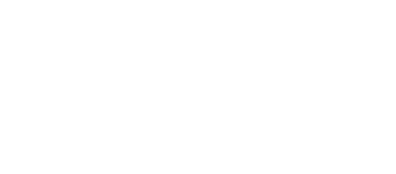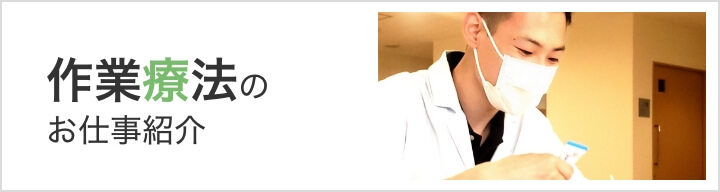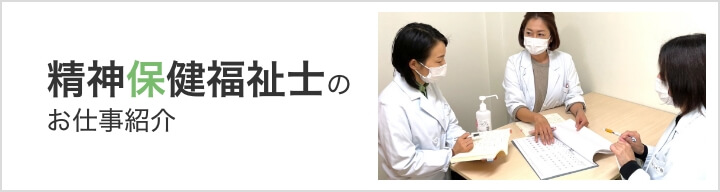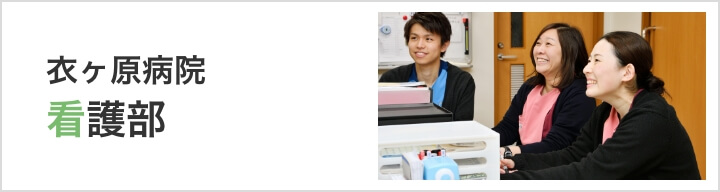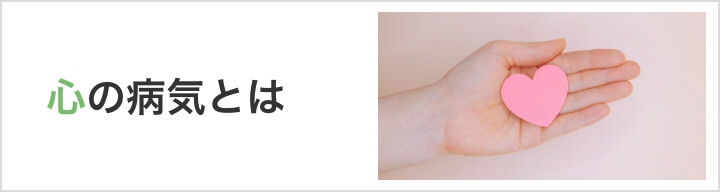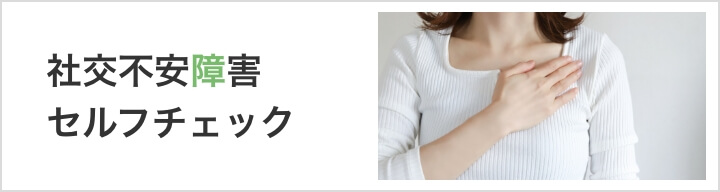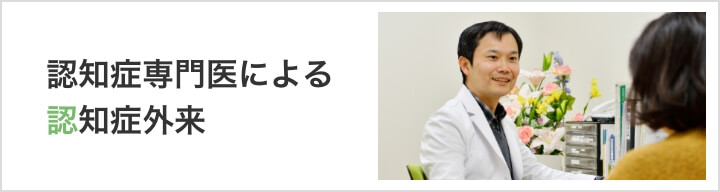2022.12.15 お役立ち情報
認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)とは?

「行動・心理症状(BPSD)」
認知症の症状のうち、認知機能の低下などの中核症状を原因として二次的に起こるものをいいます。
「行動・心理症状(BPSD)」と呼ばれています。
中核症状は記憶の障害、理解・判断力の低下、実行機能の障害など、
脳の機能低下によっておこる変化です。
BPSDは
「気分が落ち込み表情がくらい」、
「怒りっぽい」
「見当識障害によって道が分からなくなり、徘徊が起こるようになった」
といったように、
中核症状より引き起こされる行動や症状のことを言います。
その症状や程度は、すべての認知症の人が同じではなく、
個人差が大きく症状の現れ方や程度は人によって異なります。
BPSDの症状とは?

「行動・心理症状(BPSD)」の症状には主に以下のようなものがあります。
1.不安感・抑うつ感
認知機能が低下することによりできないことが増えて日常生活に支障が出てきます。
それにより患者様が不安を感じたり、気分が落ち込み抑うつ状態が見られるようになることがあります。
2.徘徊
時間や場所が分からなくなる見当識障害などが原因で起こります。
徘徊は事故や行方不明の危険性があるため、
程度がひどい場合はGPSなどを使った市の見守りサービスの利用など安全対策を取ることが大切です。
3.幻覚(幻視など)
幻視は、レビー小体型認知症で多いですが、ありありとしたものが見えることで、
例えば「子供や小動物が部屋にいる」と話すなど、視覚的な幻覚のことを幻視といいます。
ほかに幻聴、幻味、幻臭、体感幻覚など認めることもあります。
4.暴力・暴言、介護抵抗
いらいらして、暴力・暴言がひどくなることがあります。
認知症になる前は穏やかな性格だった人が、人が変わったように怒りっぽくなったり、暴れたりする場合もあります。
これにより介護の介入が難しいことがしばしばあります。
5.物盗られ妄想・せん妄
「物盗られ妄想」は、アルツハイマー型認知症でよく見られる症状です。
身近な人に対し「盗まれた」という被害的な妄想を向けるようになります。
また、体調不良や環境の変化によって見当識障害が起こり、
時間や場所が分からない、幻覚を見る、イライラする、興奮するといった
「せん妄」や逆にウトウトして活気がなくボーとしている「(活動減少型)せん妄」が現われることもあります。
また上記以外にも失禁・弄便、性的逸脱、易怒性・興奮などがあります。
認知症に関する症状は専門機関で相談を

BPSDは認知症の進行具合と関係なく出現するため、
認知症の初期からみられることもあり介護をする上でとても問題になります。
BPSDがひどいと、適切な介護サービスが受けられなかったり
在宅困難や施設入所困難など様々な弊害がおこります。
そのため、BPSDをコントロールするためには専門医への受診が不可欠です。
当院では認知症の専門医による認知症外来を行っています。
BPSDでお困りの場合やご相談したい場合はお気軽にご相談ください。
カテゴリー一覧
- 月別アーカイブ
-
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
最近の投稿
- 2025.04.1大切なお知らせ 加藤豊文医師の診察受付時間変更のお知らせ
- 2025.04.1大切なお知らせ 5月17日(土)代診のお知らせ
- 2025.03.7お役立ち情報 認知症初期症状について〜本人及びご家族の認知症の始まりに気づくポイント〜
- 2025.03.1大切なお知らせ ゴールデンウィークお休みのお知らせ
- 2025.02.20お知らせ 広報誌『こころも』vol.6 発行のお知らせ


その他のご案内
More Information
出版書籍のご案内
Publications
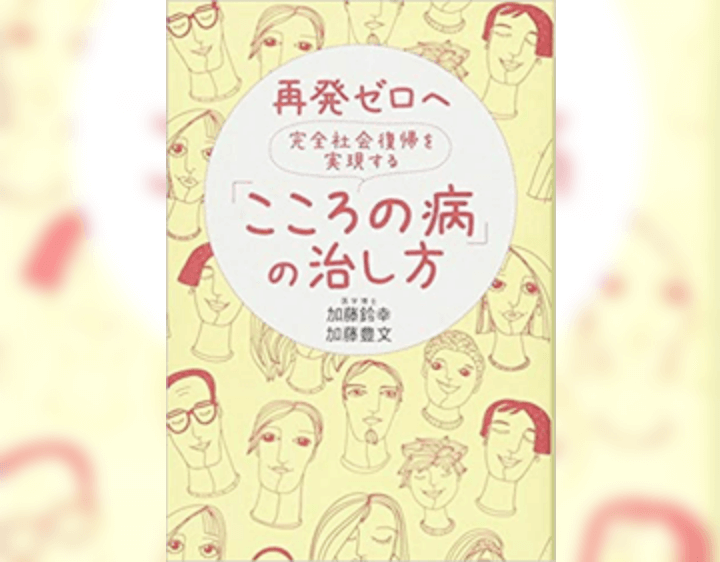
再発ゼロへ 完全社会復帰を実現する
「こころの病」の治し方
当院理事長 加藤鈴幸医師と副理事長 加藤豊文医師の著書が出版されました。
全国の書店またはAmazon等のオンライン書店でご購入いただけます。